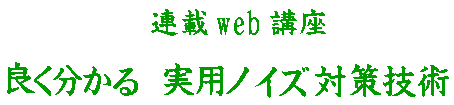
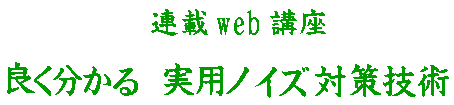
◆ アナログ回路には、パッシブ回路とアクティブ回路とがあります。簡単な回路にはパッシブ回路が用いられます。しかし、複雑な回路や高精度を要する回路にはアクティブ回路を使用します。
アクティブ回路の基本は、オペアンプ 回路です。ここでは最も一般的な、オペアンプ回路を取り上げます。オペアンプによる増幅回路には、反転増幅回路と、非反転増幅回路とがあります。
これらの増幅回路の、オペアンプ外付けの抵抗を、インピーダンスに置き換えると、さらに一般化された、アクティブ回路になります(図.1)。
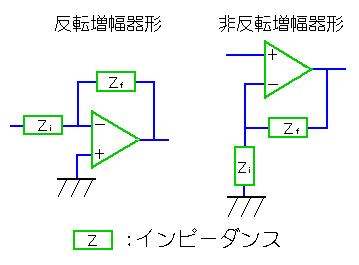
◆ 図.1 に示したアクティブ回路が、複数組み合わされて、アナログ回路を構成します。その最も基本的な構成は、図.2に示すように、1つの出力が、他の入力になった形です。
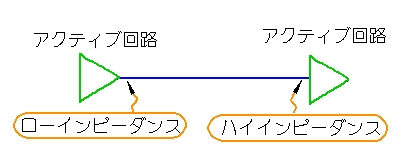
◆ 図に示すように、アクティブ回路の出力インピーダンスはローインピーダンス、アクティブ回路の入力インピーダンスはハイインピーダンスです。
一般に、アクティブ回路の出力は、オペアンプの出力です。オペアンプ単体の出力インピーダンスは、もともと低いのですが、使用状態、すなわち、フィードバックを掛けた状態では、さらに一層低くなります。
アクティブ回路の入力は、非反転増幅器形は、オペアンプの入力ですから、極めてハイインピーダンスです。反転増幅器形の場合には、入力側に接続された素子のインピーダンスの値(図では Zi)になります。この場合も、通常は十分大きな値です。
◆ オペアンプの増幅率には、周波数特性があります(図.3)。
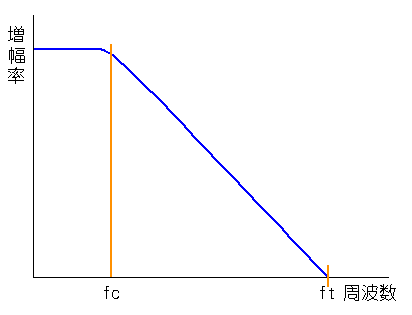
◆ 周波数特性の形は、1次フィルタと、ほぼ、同じです。低い周波数では、十分に高い増幅率を持っていますが、高周波の阻止域では、-20dB/dec (dec は 10 倍)で減衰します。したがって、図に示すように、カットオフ周波数 fc が存在します。
高い周波数では、増幅率が 1(0dB) となり増幅作用が無くなってしまいます。この増幅率が 1 となる周波数のことを、ユニティゲイン周波数 (ft)といいます。
阻止域において-20dB/decで減衰することから、阻止域においては、その任意の場所における、周波数と増幅率(dB値)との積は、常にユニティゲイン周波数と、同じ値になります。この積のことを利得帯域幅積 といいます。
ユニティゲイン周波数は、低速のオペアンプでは、1MHz程度またはそれ以下で、汎用的なもので10MHz程度です。
◆ したがって、通常のプリント基板内の配線では、リンギング周波数は、ユニティゲイン周波数よりも高く、リンギングの元になるものがありませんから、リンギングは発生しません。
しかし、高速オペアンプでは、ユニティゲイン周波数が100MHz以上のものもあります。この場合には,リンギングが発生します。また、長距離伝送では、低い周波数で、リンギングが発生します。
リンギングが発生しない条件におけるノイズの発生は15.(2)に、その考え方および対策は15.(3)に示しました。
◆ アナログ回路においても、トランジェントな現象は、ディジタル回路におけるリンギングと同様に、取り扱うことができます。オペアンプ回路は、図.2 に示したように、リンギング発生の条件(インピーダンスがドライバ側 低、レシーバ側 高)を満たしています。
ただし、高速のオペアンプを、除いては、通常は、リンギングは、発生しません。オペアンプの周波数特性が、リンギングの周波数をカバーしていないからです。
アナログ回路では、リンギング発生条件にある場合には、トランジェントではなく、定常的な現象としてとらえることが必要な場合があります。
◆ 先ず、定在波と呼ばれる現象を説明する必要があります。図.4は、定在波の現象を見るための、シミュレーション回路です。図において、ドライバ、レシーバは、共に、オペアンプ回路です。ドライバからは、正弦波を出力しています。
[注] シミュレーションの詳細については、別の講座「自動制御」の 2.1 を参照してください。
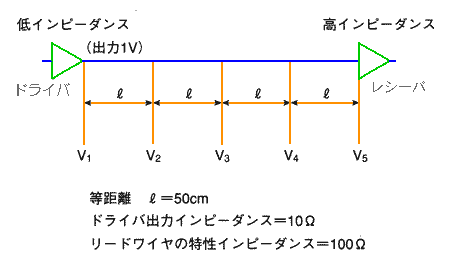
◆ 図.5は、図.4 の回路のシミュレーション波形です。(a)は、レシーバ側に終端抵抗を入れて、反射を無くしたものです。信号は一定の速度で進んでいますから、測定点によって、逐次位相がずれています。
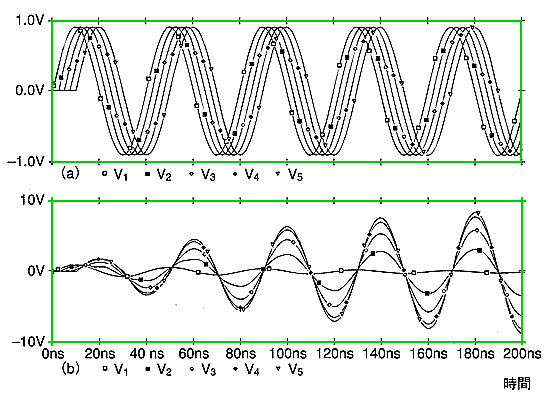
◆ しかし、通常、低周波のオペアンプ回路では終端しませんから、反射が起こります。このときの波形が(b)です。反射によって信号が、伝送路を、何回も往復するので、共振が発生して、振幅が増大します。
このときは、各部の信号は一斉に動きます。すなわち各部の信号の位相は等しく、波動としての進行がありません。
このような波形を、定在波 といいます。これに対して、通常の、(a)に示すような波形を、進行波 と呼びます。
◆ この共振が発生する条件は、信号線の長さが、信号の1/4波長のときです。また,その奇数倍の周波数でも共振します(図.6)。
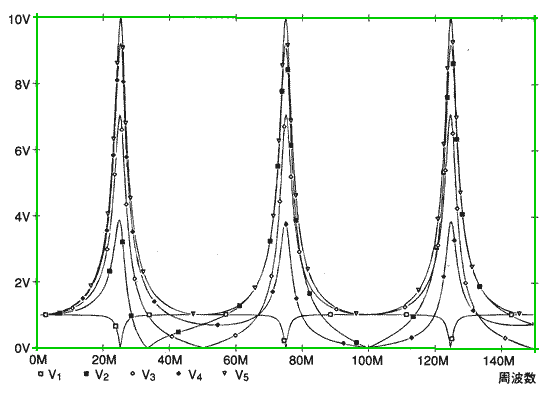
◆ 共振の振幅は、信号線の長さ方向の位置により異なっていることが分かります。
最大振幅は、レシーバの入力インピーダンスが十分に高い条件では、ドライバの出力インピーダンスを Zs、信号線の特性インピーダンスを Zc とすれば、Zc/Zs 倍になります(この例では10倍の10V)。
信号線の長さ方向の位置による振幅を、図.7に示します。
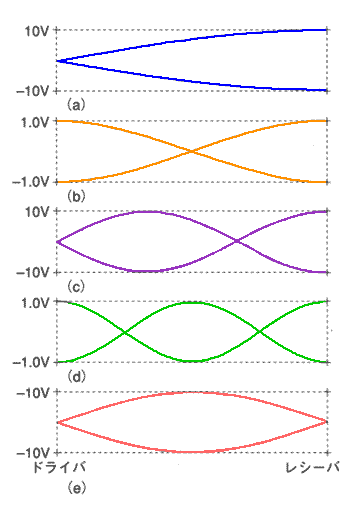
◆ この波形は,定在波に固有の波形です。波形は正弦波形またはその一部になっています。
共振による定在波の波形には、電気信号の反射のよるもの以外に、代表例として、ピアノの弦や、笛の管などがあります。図には、このシステムだけでなく、これらが示す波形も含んでいます。
図の(a)および(c)が、このシステム(図.4)に対応する波形です。ドライバのインピーダンスが低いので、ドライバ側の振幅が小さく、レシーバのインピーダンスが高いので、レシーバ側の振幅が大きくなっています。
(a)は図.6に示す基本周波数(左側のピーク)に対する波形で、(c)は、共振周波数が3倍のとき(図.6 の右側のピーク)の波形です。
(b)、(d)は、管(両端開放)における波形です。(e)は、弦における波形で、管(両端閉)の場合にも存在します。管の場合は,管の端が開放であるか、閉じているかによって、端における振幅が決まります。
(b)、(d)の波形は、信号線においても、存在する波形です。(b)の波形は、図.8のときに発生します。
[図.8] 図.7(b)の波形になる条件(中央にドライバがある)
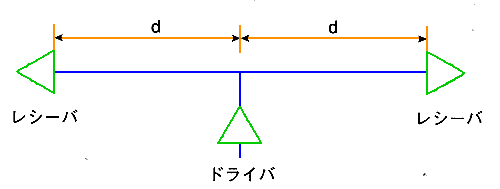
◆ ドライバの位置が中央ではなく、1/4のところにあれば、図.7(d)の波形になります。
なお、以上の各波形は、シミュレーション波形です。実際には、シミュレーションで無視した要因によって、共振周波数がずれたりします。
しかし、いずれにしても、このような波形では、信号を伝えることはできません。
◆ 信号を、精度高く伝えるためには、共振の影響が無視できる条件でなければなりません。オペアンプの速度が遅くて、共振が発生しない条件であれば、共振は発生しません。
共振が起きる条件のときは、共振により発生する誤差が、許容誤差の値よりも小さければよいわけです。
図.9は、図.6の周波数の低いところを拡大したものです。振幅だけでなく位相も示してあります。
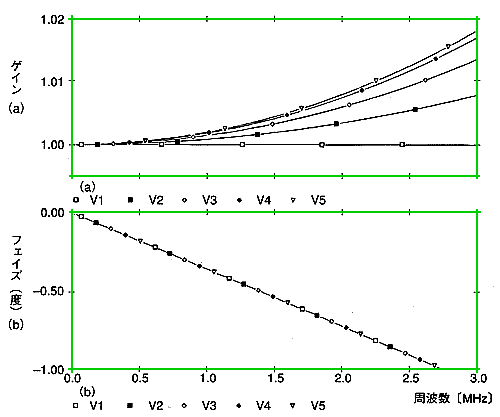
◆ アナログにおいては、ノイズの影響は、ノイズによって引き起こされる誤差の大きさで評価します(1.(6-B)参照)。
共振の問題においても、振幅および位相が、所定の許容誤差以内に収まる周波数範囲が、実用可能な範囲です。
信号を最も多く利用するのは、レシーバ側の端です。そしてここが最悪条件です。このレシーバ端における、信号線の長さ、信号周波数および振幅誤差の大きさの関係を図.10に示します。
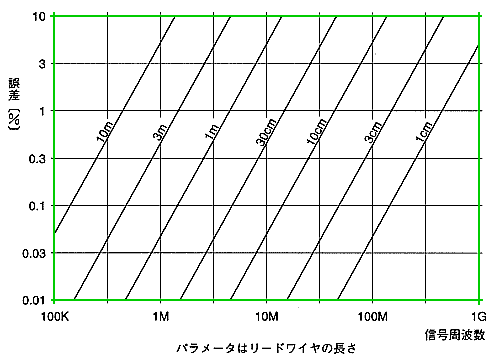
◆ この図は、オペアンプが高速で、共振が発生する条件の場合を示しています。
オペアンプが高速であっても、信号の周波数がオペアンプの性能に比べて低いときは、ローパスフィルタを挿入して、共振を抑えることもできます。
信号の周波数が高いときは、終端して反射を防ぐことにより、共振の問題を無くす方法もあります。しかし、完全な終端を行うことは必ずしも容易ではありません。また終端に伴う誤差の発生もあります。
◆ 高精度かつ低歪のシステムを構築するためには、終端しないで、図.10によって、十分に誤差が小さくなる条件の範囲で使用することが、必要です。
しかし、高周波では、通常は、波形歪みが問題であり、振幅の精度が高いことが、要求されることは、余りありません。このような、場合には、終端する方が、実用的です。